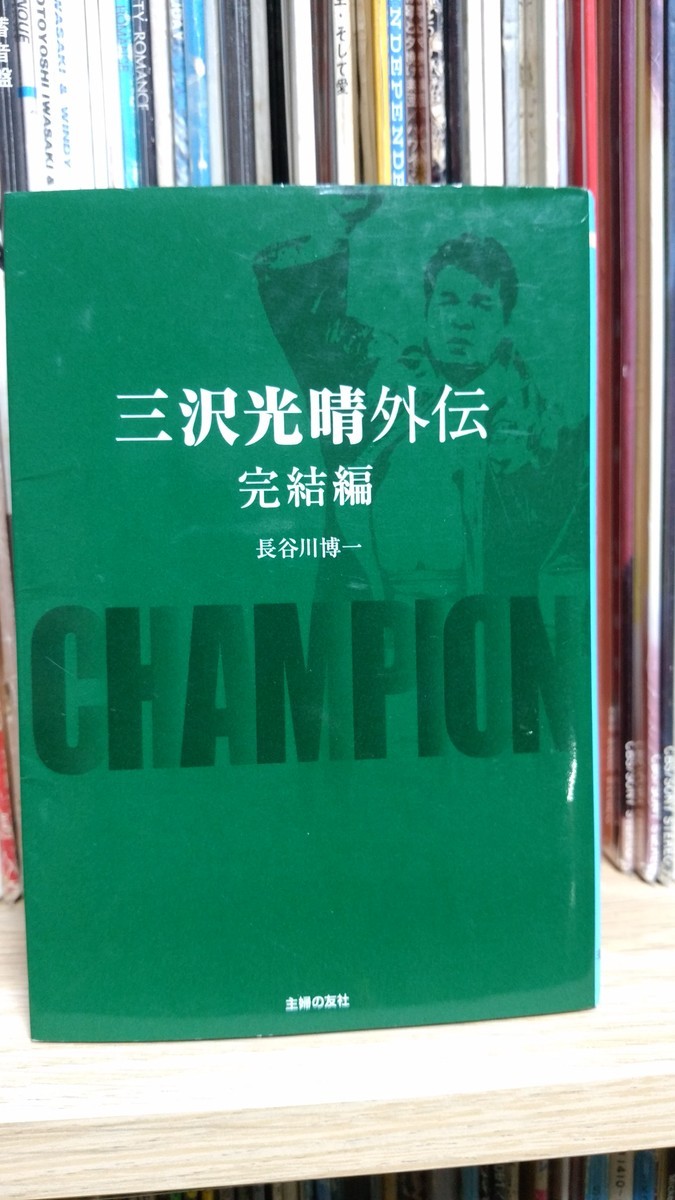連載を胸躍らせながら読んでいたので、こんなに突然のお別れになってしまうとはいまだに信じることができない…音楽ライター、本物の音楽ジャーナリストだった長谷川博一さんのことだ。細野晴臣が1976年に残したトロピカル三部作の第二章『泰安洋行』を関係者のインタビューや分析を交えて深掘りする、という2016年7月~2018年11月のレコードコレクターズ誌連載がこの度一冊の本、長谷川さんの遺作として世に出た。当時連載を読んでいて、久々にお金を投じる価値のある雑誌記事を読んだ気持ちになったことを思い出すし、長谷川さんも、近年の音楽評論の低潮を憂いつつ持ち前の気概で書いた文章だと推測する。ワールドスタンダード鈴木惣一朗さんのあとがきもまた不思議なもので、アパートでレコードを聴き合う良き友人だったふたりが30数年ぶりに再会、打ち合わせ中に「(入院して)声帯を除去するかもしれないから、話すのは最後になるかもしれないなぁ」と(長谷川さんから)知らされ、数日後に訃報を聞いたのだと…さらにその数ヵ月後「長谷川博一」という着信が鈴木さんの携帯に鳴り、リダイヤルすると、見知らぬ人が出て…それを長谷川さんが託したメッセージと受け取ってこの本は完成したそうだ。

個人的には中高生の頃、NHK-BSロック大全集という洋楽の生演奏(しかもサタデーナイトライブ!)を流してくれる番組に夢中になった。YouTubeもなく、動くミュージシャンをおいそれと観れなかった時代。動くジャクソン・ブラウン、ランディー・ニューマン、ポール・サイモン、ジェイムス・テイラー、ニール・ヤング、ボブ・ディラン…ビデオテープが擦り切れるくらい観ました。そこに南こうせつ、奥居香と一緒に出演していたのが気鋭の若手音楽評論家・長谷川博一その人。ロック世代のミュージシャンと同世代の評論家にありがちな(悪くいえば)「俺たちの~」「マブダチの~」といった暑苦しく独善的なスタンスとは対照的で、長谷川さんの知的/クールかつ俯瞰的なまなざしと、音楽への温かい理解・飽くなき愛情・包容力に、私はロックやフォークといった音楽に接する態度そのものを教わった。

初めてお会いしたのは、これまた私の人生を変えることになるエレックレコードの方々が再集結した「エレック唄の市2009」(於・九段会館)。たしか前座の演奏とケメさん、生田敬太郎さんあたりを見た後でロビーに出たら、一目で「あっ長谷川さんだ!」と。大柄でネルシャツがとてもよく似合っていた。恐れを知らぬ私が、「NHK-BSの番組の大ファンでした」…なんて話しかけると、とても喜んでくれて、ライブのセットリストを見せてくれた上で「じゃあ飲みに行きますか、でもチケットせっかく買って来てくれたのに悪いかな…」なんて。でも二つ返事で飲みに行くことになって、お茶の水の行きつけの店でご馳走になった。
その時、長谷川さんは海野弘の1930年代論を読んでいたけれど、きっとミュージシャンの楽曲ないし背景を理解するためだったのだと思う。本物だと思った。音楽活動を再開したケメのイノセンスの話に始まり、大好きなロックの話、フォークの話、長谷川さんが雑誌『This』はじめ深く関わっておられた佐野元春さんの話、スプリングスティーンの話、ビートニクの話、エキゾチカの話、政治の話、教育の話、プロレスとロックは似ているという話、仏教にいま関心があるという話…結局話が尽きず、山の上ホテルのバーに場所を移し、ただただ音楽のことや政治のことを話した。純粋に音楽のことが大好きな姿に感動するとともに、初対面の単なる若輩音楽ファンだった私に、偉ぶることなくフラットに接してくれた姿に心動かされた。そして何より長谷川さんが、近代化以来日本にとっていまも永遠のテーマである、西洋との狭間で表現することの有り様を深く考え抜く姿に、感銘を受けたのだった。

これは、細野晴臣のセルフオリエンタリズム全開のトロピカル三部作を論じた今作『追憶の泰安洋行』や2013年の労作・宇崎竜童との編著『バックストリート・ブルース 音魂往生記』(白夜書房)(この本、小川真一さんがインタビューを手掛けた荒木一郎『まわり舞台の上で』と共に、古井戸・加奈崎さんの本を作るときの参考にした)にも通底している。そもそも出世作だった『Mr.OUTSIDE わたしがロックをえがく時』(1991年、大栄出版)、『きれいな歌に会いにゆく』(1993年、大栄出版)で、長谷川さんがソングライティングについてインタビューを行った桑田佳祐、忌野清志郎、宮沢和史、佐野元春、泉谷しげる、山口洋、中川敬、小田和正、吉田美奈子、矢野顕子、近田春夫、浅川マキ…彼らの価値が30年経っても古びない理由を考えてみてもよいだろう(ちなみにこの本、佐野さんの番組「ザ・ソングライターズ」のアイデアとなったのでは?と長谷川さんに聞いた時、明確な返事はなかったけれど、長谷川さんが亡くなった際、佐野さん自身によって「振りかえれば、この番組を企画した時、長谷川さんの本のことが記憶にあったのだと思う。そのことに感謝の気持ちを伝えたかったが叶わなかった。」と種明かしされた)。
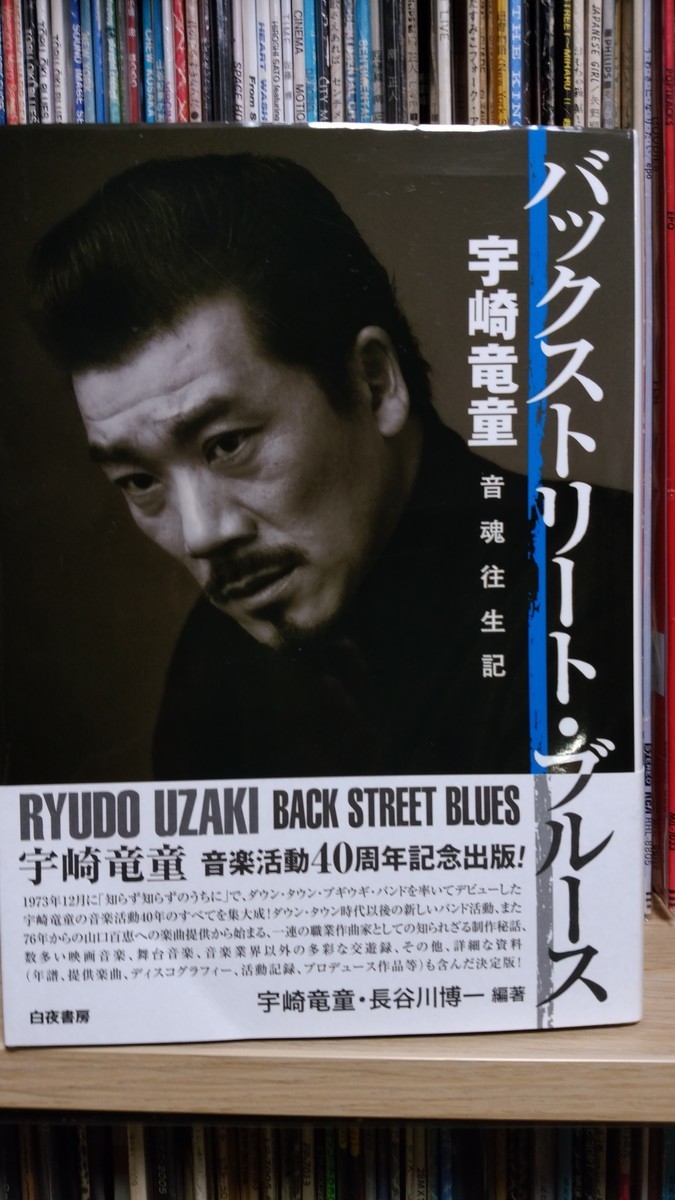
『追憶の泰安洋行』にこんな一節があった。「日本の音楽表現は今、音楽そのものと音楽を使った何か別ものの芸能とに分かれているように思う…細野バンドの面々が生み出すものは、音楽そのもの」…音楽を長く愛してやまないファンの方ならきっとわかって頂けると思う。矢沢永吉さんの取材前日にこんなメールを頂いたこともある。「はっぴい以降の同様の流れを汲む国内アーティストで佐野さんと同じくらいの影響力(知名度も含め)を持つ人がきわめて少ない、ということが日本のロック界の大きな不幸なんですよね。」「佐野さんレベルの知力の人が後塵にもう5人くらいいたら日本の業界も、もっとロック的だったろうなと思います。そのうちの一人が自分ではないかと勝手に自認してもいるのですが。」…この長谷川さんの言葉にも深く同意するほかない。「きっと石浦さんだったら、「ランニング・オン・エンプティ」とプロレスの意味の相似を理解してもらえるのではないかと思います。」とメールを頂いた後に読ませて頂いた『三沢光晴外伝』。長谷川さんのアナザーワークの中でも指折りの名著だった。その後、しばらく連絡が取れなくなってしまって、昨年の訃報を聞いた。それでもまた、いつかどこかで、お会いできると信じている。これからも、長谷川さんがそうであったように、音楽を信頼していきたいと思う。