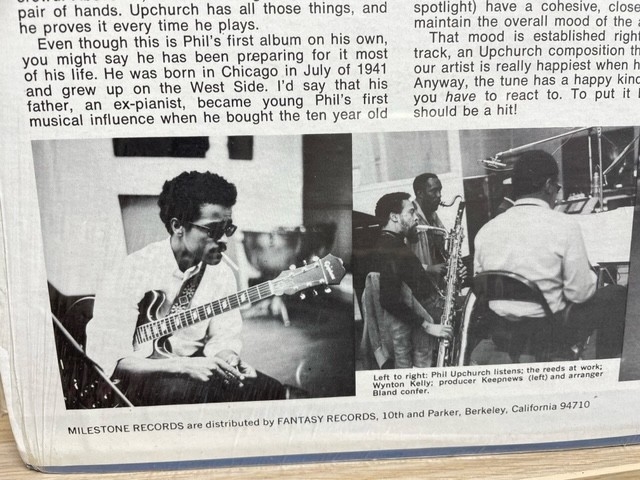*[SSW] Gary Benson / Reunion ( Bigpink / 1970 )

イギリスのシンガー・ソングライター、ゲイリー・ベンソンの幻のファースト『reunion』。韓国ビッグピンクのリイシューで CD化された後、中古アナログが市場に出てますけど、いまだに5桁…(笑)。ビッグピンクも売り切り商法なので、どうせYouTubeで誰かがアップロードしちゃうんでしょうけれど、音楽業界のためにもちゃんと買いました(これ重要)。mp3とは違って、ちゃんとしたCDプレイヤーとアンプで聴けば明らかに音も良いし。
ゲイリー・ベンソンの代表曲はオリビア・ニュートン・ジョンが取り上げて1975年にヒットさせた”Don't Throw It All Away”。『サタデー・ナイト・フィーバー』で知られる俳優ジョン・トラヴォルタの”Let Her In”や、レゲエのマキシ・プリーストが取り上げた”Close To You”もあった。彼自身のレコードだと続く1973年のセカンド『The Concert』は日本でCD化されている。

1975年のサード『Don't Throw It All Away』と1977年の『New World』はドイツ辺りから取り寄せて以前手に入れたものが手元にある。すさまじく良いバラードが満載。日本では1980年の4枚目『Moonlight Walking』がAOR名盤として結構売れた。ゲイリー・ベンソンっていやに分かり易い名前だなあと思って調べると、本名はハリー・ハイアムスとあるので、ユダヤ系ではないかと思われる。ユダヤ系の苗字は西洋では偏見のタネになるので、名前を変えることが多い。アメリカでもボブ・ディランはじめ例に事欠かない。


で、初めて聴きましたがこのファースト、ソフトロックのブーム全盛期にリイシューされていたら、誰もがぶっ飛んだんじゃないでしょうか。初期のCCMっぽい、宗教っぽさを感じるモノクロのジャケにだまされてしまったけれど、全曲凄まじいクオリティにびっくり。前に出ているベースの立ち上がりも含め、イギリスのジミー・ウェッブという惹句は嘘ではない。メロディー・ラインに似たものを感じる曲もあるのだけれど、ジミーより歌が上手かったりもするし、ストリングスの気品と弾むようなビートで展開される英国ポップの王道にはひれ伏すほかない。ジョージー・フェイムが取り上げた”Going Home”(コレもソフトロックのブームの中で再発されて一気に有名になった)のオリジナルも収録。リリース元のPenny Farthing Recordsはキンクスを手掛けたラリー・ペイジのレーベルで、サマンサ・ジョーンズ盤なんかが出ていた。あと、ゲイリーの初期の提供曲の中にはヴィグラス&オズボーンのポール・ヴィグラスが歌う”Stop”なんてのもあったり。いやはや私はアメリカ偏愛なので熱心には掘り下げていなかったけれど、英国モノは奥が深くて困る。